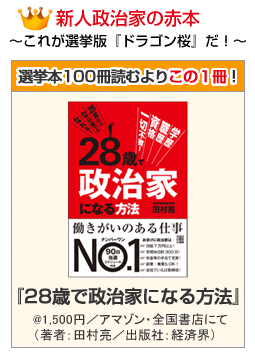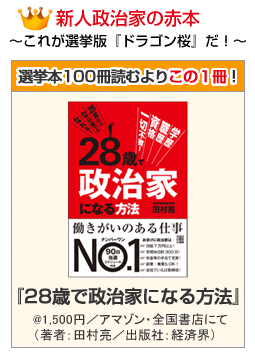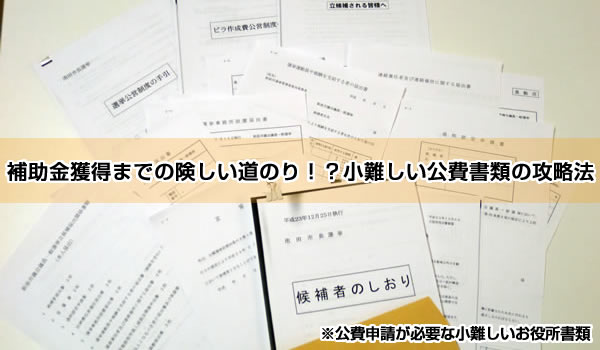
公費負担制度の実際のお金の流れは、役所の会計局部門から直接選挙用品制作会社にお金が支払われます。
候補者は何をするかと言えば、制作会社との契約や役所の出金手続き書類など、多いと数十枚のお役所書類の記入が必要になります。
お役所の書類である以上、読んでも「で、何が書いてあるの?」と問いただしたくなるような意味不明の小難しい書類で、必須記入箇所、未記入箇所、ハンコの位置などややこしいことだらけ。

私も昔、初めて公費書類を書いたときは、徹夜しても訳が分からず記入ミス連発、何度も書類を取り寄せて何時間もかけたことは忘れられません。
あきらめたいところですが、書けないと数十万円もの公費の補助金が貰えず、自腹となってしまいますので、多くの新人候補者は、政治活動を断念して書類に集中したり、役所まで聞きに行ったりと活動に集中できない本末転倒な状態に陥ります。
唯一の攻略法は、"慣れている人に頼む"ことです。
後援会で選挙書類記入の経験のある人がいればいいのですが、慣れている人はなかなか見つかるものではありません。
そんなときは手前みそで恐縮ですが、弊社のような選挙用品専門会社に公費書類のお手伝いを含めて選挙ポスターなどを依頼するという手が最もスマートです。
必要な書類もそうでない書類も判断に迷ったら、まとめてお送りください。弊社で記入する書類、
お客様が書く書類など分別し、自署押印部分は付箋をつけてお戻しするなど完璧な公費書類の書
き方指南をさせていただきます。
(「どの公費書類を送ればいいの?」という判断ができない場合でも大丈夫。
たとえ無関係の書類が混入していても振り分けてそのままお戻ししますのでご安
心ください)
公費負担制度は、参政権に基づく候補者の権利です。
出し忘れや、届出のミスでせっかくの公費が頂けず、自腹となってしまっては大変ですので、重要な書類の記載代行またはお手伝いのサービスのある専門家を探しましょう。

公費負担制度とは、"候補者の選挙費用の一部を公的補助で自治体が負担してくれる制度"です。ではなぜ、選挙に出る人に公的な補助がでるのでしょうか?
ご存じの通り、日本人には人権として「参政権」≒「立候補の自由」が認められています。しかし、選挙はとてもお金がかかります。立候補の意思があっても、一定の財力がなければ現実的に出馬できません。
せっかくの"立候補の自由"という人権も絵に描いた餅となってしまいます。
また、経済力によって選挙PRに差が出てしまって、当落が決まってしまっても、民主主義の観点から見たら「結局、民意も経済力次第かよ」となってしまいます。
選挙の公費は"お金持ちだけに限らずとも出馬ができるという民主主義の参加の枠を広げる考え"と、"経済力によってアンフェアな選挙を防止すること"の2点がその趣旨の根底にあるのです。

無限に公費がまかなわれるのではなく、一定の制限、適用範囲があります。
選挙の種類によって、異なります。詳しくはお問合せ下さい。

この公費に関しては、一定の得票数を確保しなければ、補助が受けられないルールがあります。
これは単なる売名行為での出馬人には、公金の補助は無いという意思表示です。
通常、市議会であれば、ボーダーとなる得票数は、100〜300票ほどです。
(供託金没収票数=有効投票総数/議員定数×1/10)
と言いましても、地方議会選挙においては、公費負担が貰えないほど得票数が低いというケースはまれです。

公費負担制度は、候補者の権利として認められた制度であり、利用の有無で50万円以上(選挙種類によりますが)の私費を削減することもできますので、積極的に活用したいものです。
中には、そういうお金の補助が気持ち悪いという方もいらっしゃいますが、一回ここで公費負担を"借りる"と考え、当選し仕事で返すという考えにしてはいかがでしょうか?
もちろん主義を破って何としても使えという訳ではありませんが、末永く政治家を務めて頂くには、やはり、最低限の経済力があったほうが良いかと思います。
具体的な公費負担制度の活用方法、自分の選挙でも使えそうか?等の質問も良く頂きますので、お気軽にご相談ください。
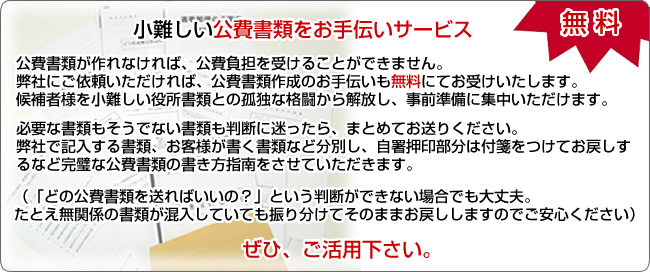
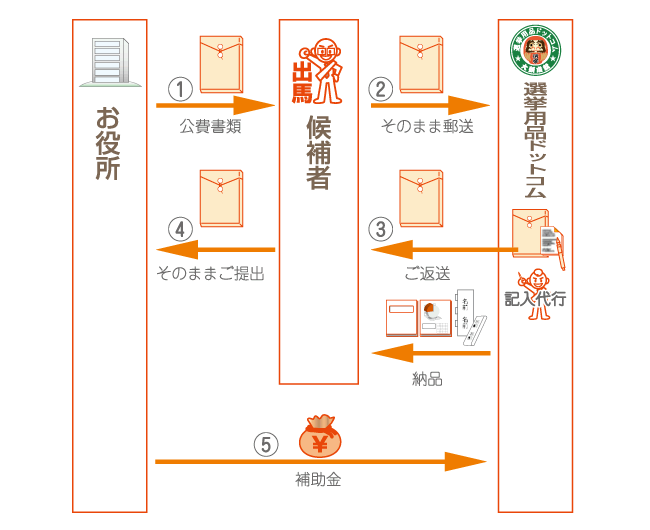
|